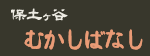|
~ 伊勢から江戸を目ざしてやってきた夫婦白狐のお話 ~ |
■ 昔々、保土ヶ谷宿のある旅籠(はたご)に一人の女がやってきました。
|
私は伊勢からまいりました。名は「さい」と申します。
先年は江戸から大勢の人達が御蔭参り(おかげまいり)に訪れ、伊勢の地がたいそう繁昌して、それは有り難いことでございました。その上、華やかな江戸の話を伺うことができて、私たち伊勢の住民も心弾む毎日でした。そうこうする内に皆さんが帰って、いつもの静かな日々がやってきた時、今度は私たちが江戸へ行ってみたいと願うようになりました。 そこで夫と二人で相談の上、一大決心をして江戸へ向かうことにいたしました。伊勢を出てからは、見るものすべてが珍しく、道行く人達も親切で、たいへん楽しい旅を続けてまいりました。ところが三島の宿を過ぎ箱根の山にさしかかった時、夫は急な病に倒れ、十分な手当もできぬまま帰らぬ人となってしまいました。私一人伊勢に引き返そうかとも思ったのですが、それでは夫の意志に背くことになります。形ばかりの弔いを済ませて、どうにか保土ヶ谷までやってまいりましたが、江戸までもう一息というところで路銀(ろぎん)を使い果たしてしまいました。頼るところもありません。どうかこちらの旅籠でしばらく女中に使っていただけないでしょうか。どんなことでもいたします。 |
それから毎日、さいは朝早くから夜遅くまで、それは真面目な仕事ぶりでした。どんな仕事も器用にこなすばかりか、読み書きそろばんも達者なことから、旅籠ではたいそう重宝がられました。
ところが主人には二つばかり腑に落ちない点がありました。
「色白で細面の美しい女なのに、宿場の男共は噂をするばかりで誰も言い寄らないのはなぜか。それに毎夜どこへ帰って行くのか」と。
ある時、旅籠の番頭が夜道を帰るさいの後を付けて行くことになりました。かすかな月明かりを頼りに追うこと四半時(30分)、街道からそれて山道を進み、やがてさいは朽ちかけた炭焼き小屋に入って行きました。番頭は物陰から小屋を見張ることにしました。それから一時(2時間)ほど経った頃、突然小屋から光輝くばかりの白狐が飛び出して行きました。番頭は我が目を疑いました。
小屋に入ったのはさい 出て行ったのは白狐
さいと白狐が一緒にいるはずはない
とすると・・・ いやいやそんなことはない
番頭はそのままじっと待つことにしました。
東の空が明るくなり始めた頃、意を決して炭焼き小屋を覗くと・・・
誰もいない! さいはどこへ・・・ やっぱりあの白狐が・・・
番頭は一目散に駆け戻り、主人に事の次第を報告しました。ところが主人は、「待ちくたびれて夢でも見たのだろう、時間になればやってくるさ」と、番頭の話を全く信じませんでした。案の定、番頭の心配通り、さいはいつもの時間になってもやってきませんでした。翌日も翌々日も。結局、さいは二度と旅籠には現れませんでした。
普通、旅籠の女中が一人いなくなっても、それほど話題にはなりませんが、飛切りの美人女中となれば話しは別です。思いを寄せていた男共が黙ってはいません。「○○屋の女中が神隠しにあった」との噂が保土ヶ谷中に拡がったのです。
噂が拡がるにつれ、その旅籠に次々と災いが降りかかってきました。丁稚が牛車に轢かれて大怪我をする、風呂場がボヤになる、番頭が病に倒れる、宿泊人の荷物が紛れる、帳簿が合わない、宿役人からお咎めを受ける、客が減る・・・ 旅籠が急激に寂れ始めたのです。
さすがに気丈な旅籠の主人も、「番頭の言う通りだった。江戸へも行けず伊勢へも帰れぬ夫を失ったひとりぼっちの女狐が、住処を暴かれたために行き場を失って嘆き悲しんでいるのだろう。ならば立派なお社を造ってやろう。 名前がさいで尾っぽのある利発な女中だった・・・、そうだ 尾才女(おさいじょ)稲荷と名付けよう」
【保土ヶ谷本陣文書・寛政十一年(1799)社寺書上帳】に、
一、正一位尾才女稲荷 寛政九巳正月日(1797年) 本宮祠官 松本筑後守
とあります。 200年以上前のお話です。
■昭和の初め頃まで、藤塚から法泉にかけての山間では、時々白狐が見かけられたそうです。実際に出会った人の話によれば、少しポッチャリとした美人狐だったそうです。 ただし、尾才女狐ゆかりの狐か、或いは全く別の狐か定かではありません。一般に狐は人をだますと言われていますが、尾才女狐は決してそのようなことはありませんでした。出会った人に幸運をもたらすと信じられていたそうです。その後、尾才女稲荷は保土ヶ谷バイパスの開設やマンション建設工事のために二度場所を移し、平成11年12月、現在の地に新しい立派な社殿が造営されました。
 ■ 江戸時代、御蔭参り(おかげまいり)と呼ばれる大群衆による熱狂的な伊勢神宮参拝運動が全国各地で起こりました。
■ 江戸時代、御蔭参り(おかげまいり)と呼ばれる大群衆による熱狂的な伊勢神宮参拝運動が全国各地で起こりました。当時の旅人にとって、往来手形はなくてはならないものでしたが、御蔭参りの場合は例外でした。手形もなく、主人や親の許可を得ることもなく、仕事を中途で投げ打って、衝動的に出かけて行ったそうです。当然、路銀(ろぎん)の持ち合わせもなく、着のみ着のまま、それでも伊勢まで旅ができたのは、沿道の人々の中に、彼らに対して金品を施したり宿泊の世話をしたりする者が少なくなかったからだと言われています。また、そうした参拝の方法を「抜け参り」とか「抜け参宮」と呼び、帰ってからも罰せられない習わしだったそうです。
江戸時代を通して御蔭参りは度々起こりましたが、特に大規模なものは、宝永2年(1705)、明和8年(1771)、天保元年(1830)、の三回で、1705年は350万人、1830年は500万人(当時の日本の全人口3000万人)に達したと伝えられます。
上の絵は、歌川広重「伊勢参宮宮川の渡し」 安政2年(1855) 「おかげまいり」の幟が見えます。
| 【おかげ参り、町ぐるみ接待…奈良・御所市で史料発見】 (2006年4月3日 読売新聞) 「おかげ参り」の参拝者を接待した経過が記された古文書 全国から約500万人が伊勢神宮に詣でたという1830年(文政13年)の「おかげ参り」について、道中に立ち寄った約1万人の参拝者を、町ぐるみでもてなした事実を記した記録などが奈良県御所(ごせ)市(旧御所町)の旧家で見つかった。 宿や食料を提供した接待のほぼ全容を記している。謎が多いおかげ参りの実態を知る第一級の史料になりそうだ。 おかげ参りは江戸時代に発生した伊勢神宮への集団参拝。金銭を持たずに旅立つ人が多く、沿道の人々らの「おかげ」でお参りできたというのが語源という。 御所町は江戸時代、木綿製品や菜種油などで繁栄した商人町で、藪田貫・関西大教授(日本近世史)が旧家の蔵から冊子や巻紙など29点を見つけた。 宿泊者記録の「おかけ中毎日泊名前」には、おかげ参りが始まった3月から約半年間で9729人が町内に泊まったと記載。参拝者の出身地は陸奥(青森など)から薩摩(鹿児島)まで全国各地にまたがっている。 御所町とその周辺の村が拠出した食料などの記録計1194件の中には、米5石、酒10升などを納めた裕福な油商人や、米30合を合同で寄進した長屋住民、燃料の枝11束、白ウリ1個、漬物少々を差し出した庶民らが登場。このうち御所町では全675世帯中、約7割の455世帯が寄進、町ぐるみの歓迎ぶりをうかがわせる。 御所町は、大阪と伊勢をつなぐ横大路から南に約5キロ外れているが、藪田教授は「御所町での接待の評判が広まり、伊勢参りの後、高野山や西国三十三所を巡る途中に立ち寄った人々も多かったのでは」と話す。 |